1.開発許可が必要な場合
開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設を主たる目的とした、区画または形質の変更をいいます。
開発行為に該当する場合は、原則として開発許可が必要となります。(参考:都市計画法第4条、第29条、第43条)
なお、開発許可を受けた場合、建築物の着工は、法第36条第2項の検査済証又は法第37条第1号の承認済証交付後です。
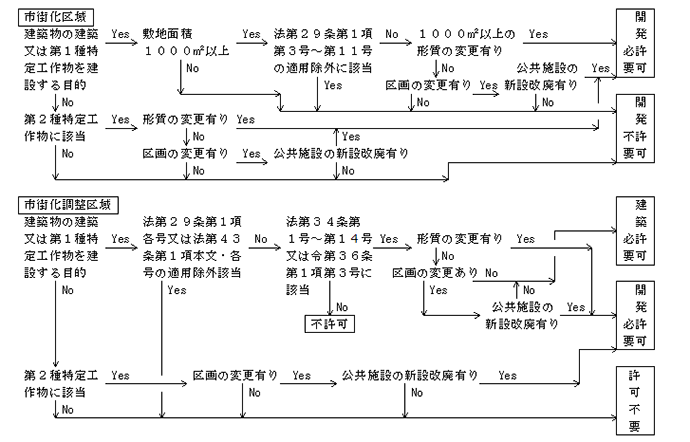
(1) 建築物の建築、特定工作物とは
- 建築物:土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの等(法第4条、建築基準法第2条第1号)
- 建築:建築物の新築、増改築および移転をいう(法第4条、建築基準法第2条第13号)
- 第一種特定工作物:周辺の環境悪化をもたらすおそれがある一定の工作物(法第4条、施行令第1条第1項)
例.コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント - 第二種特定工作物(法第4条、施行令第1条第2項):ゴルフコース、および1ヘクタール以上の運動レジャー施設・墓園
(2) 区画・形質の変更
登記簿上行う分合筆や地目変更とは関係なく、現実に敷地分割や造成を行うという意味です。
区画の変更
従前の敷地を拡張・分割・統合する場合をいいます。ただし、切土・盛土等の造成工事を伴わず、かつ、従来の敷地の境界の変更に伴い、既存建築物の除却や、へい・かき・さく等の除却・設置が行われるにとどまり、公共施設の新設・改廃の必要がないと認められる場合は、「形式的な区画の変更」とみなし、開発行為には該当しません。
形質の変更
土地の形質を変更(造成)する場合が該当しますが、以下の場合は開発行為に該当しません。
- すでに造成工事が終わっており、宅地として利用されている土地で、相当期間を経過したもの、かつ、造成工事と建築工事が連続性のない場合。(市街化区域にのみ適用)
「相当期間の経過」とは、少なくとも3年以上経過し、地形・地勢・周辺の土地利用を勘案して、必ずしも開発許可に係らしめる必要のないものをいいます。 - 30センチメートル以下の盛土、切土を伴う整地をする場合。
(3) 適用除外(法第29条第1項各号)
開発行為に該当するものであっても、開発許可は不要です。
- 市街化区域における1,000平方メートル未満の開発行為(第1号、施行令第19条第1項)
- 市街化調整区域における農林漁業用施設、および農林漁業従事者の住居の建築(第2号、施行令第20条)
- 農林漁業用施設とは、畜舎、温室、集荷施設、サイロ、農機具等収納施設等施行令第20条に定められている施設をいいます。(なお、法第34条第4号、第5号に該当するものは開発許可となります)
- 農業従事者は、専業者(純然たる地主。臨時従業者は含まない)、継続的に従事する兼業者および継続的に従事する従事者とします。ただし、当該市街化調整区域内において業務に従事する者であること。
- 公益上必要な建築物の建築のため行うもの(第3号、施行令第21条)カッコ内は根拠法
- 駅舎等(鉄道事業法、軌道法)
- 図書館(図書館法)
- 公民館(社会教育法、同法に基づかない地区集会所を除く。)
- 変電所(電気事業法)
- その他施行令第21条に定める公益上必要な施設
- 都市計画事業等の施行(第4号から第8号)
- 公有水面埋立(第9号)、非常災害のため必要な応急措置(第10号)
- 通常の管理行為、軽易な行為(第11号、施行令第22条)以下のもの等が該当します。
- 仮設建築物
- 既存の建築物の敷地内において行う附属建築物の建築
- 10平方メートル以内の増改築
- 市街化調整区域における日常生活に必要な物品の販売店舗で延べ面積50平方メートル以内で区域100平方メートル以内のもの
なお、市街化調整区域における取り扱いの定義については「4.市街化調整区域における建築確認申請の手引き」を参照してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp
