(2)家族・家庭生活と地域参加・参画について
問2「男は仕事、女は家庭」という考え方について尋ねた。
全体では「そうは思わない」が50.5%と半数を超えたが、男性は45.4%で半分に満たない。「そう思う」を男女別に見ると、女性は14.4%であるのに対し、男性は2倍近い27.4%となっている。
年齢階級別に見ると、女性は40代で「そう思う」と答えた人が3.6%と男女通じてどの年代よりも低いが、一方で「どちらともいえない」が38.4%と他よりも高くなっている。「そう思う」と答えた20代の女性の割合は、30代、40代の女性における割合を上回っている。男性は、20代、30代、40代とも約18%が「そう思う」と答えている。50歳以上の年代では、「そう思う」人の割合が8%ないし10%の差で高くなっていっている。
岐阜市で平成3年に女性3,000人を対象に行った調査では、この考えに「同感する」が18.7%、「同感しない」が26.7%で、これを本調査の女性のみの数値と比べてみると、「そう思う」は4.3%の減少だが、「そうは思わない」が2倍以上に増えている。これに伴い、「どちらともいえない」が約半分に減っている。「男は仕事、女は家庭」という考えについての女性の意識が、11年間でかなり変わったことがわかる。
平成12年の国の調査と比較すると、全体で「そう思う」は25.0%と、岐阜市の方が5%ほど低くなっている。男女別で見ると「そう思う」女性は21.4%と、岐阜市が7%低く、男性は29.6%で、岐阜市は2%ほど低い。「そうは思わない」は全体で48.3%と、岐阜市が2%ほど上回っている。(図表2)
|
項目 |
そう思う |
そうは |
どちらとも |
わからない |
無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
|
国(平成12年2月) |
25.0 | 48.3 | 25.6 | 1.0 | |
|
市(平成3年10月) |
18.7 | 26.7 | 53.4 | 1.2 | |
|
市(平成14年10月) |
20.3 | 50.5 | 26.9 | 2.3 | |
|
市(平成14年10月) |
14.4 | 55.7 | 28.4 | 1.6 |
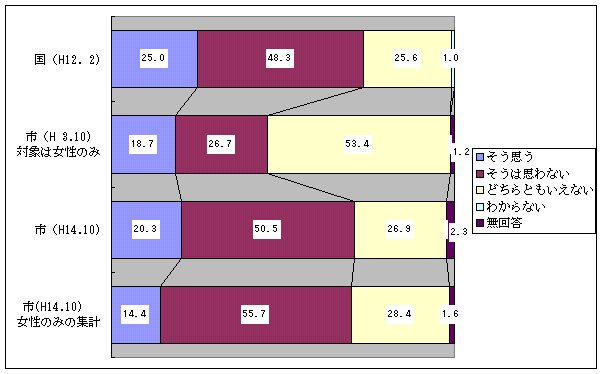
図表2 資料:「男女共同参画に関する世論調査(平成12年2月)」(国)
「岐阜市の女性の意識と実態調査報告書(平成4年1月)」(岐阜市)
問3既婚者に家事(掃除、洗濯、食事のしたく、食事の後片付け)、看病や介護、育児の分担について尋ねた。
家事のいずれについても「主として妻」が8割以上を占める。洗濯、食事のしたくは9割を超えている。「看病や介護」「育児」についても、それぞれ「該当しない」を除いた後の割合を計算すると、「看病や介護」では73.5%、「育児」では79.2%が「主として妻」と答えており、家庭生活全般において妻が圧倒的に大きな責任を負っていることがわかる。
共働きの有無で比較をしてみると、共働きの場合、そうでない世帯よりどの項目においても「主として妻」がわずかに少なく、「看病や介護」を除いて「両方同じぐらい」がわずかに増える傾向があるものの、大きな差は見られない。共働き世帯の場合でも、家事については「主として妻」がいずれも8割を超え、中でも「食事のしたく」は9割を超える。「看病や介護」については「該当しない」を除いて計算すると、「主として妻」の割合が共働き世帯において75.9%と、そうでない世帯の71.9%を上回っている。「育児」についても同じく「該当しない」を除いて計算すると、共働き世帯で78.4%、そうでない世帯で80.6%と、ほとんど差がない。女性は仕事をしながら家庭責任をも同時に担っている状況がうかがえる。
また、家事について平成14年の国の調査と比較すると、岐阜市の方が「主として妻」の割合が少しずつ高くなっている。(表)
| 項目 調査 |
主と して夫 |
両方同じくらい |
家族全員 |
子ども |
主として妻 |
その他の人 |
わからない |
無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A掃除 国(平成14年7月) |
3.9 | - | 10.2 | 1.0 | 82.4 | 2.3 | 0.1 | - |
| A掃除 市(平成14年10月) |
3.2 | 9.4 | 1.4 | - | 84.0 | 1.3 | - | 0.7 |
| B洗濯 国(平成14年7月) |
2.4 | - | 6.1 | 1.0 | 88.1 | 2.3 | 0.1 | - |
| B洗濯 市(平成14年10月) |
1.1 | 5.2 | 0.9 | - | 90.7 | 1.6 | - | 0.5 |
| C食事のしたく 国(平成14年7月) |
1.9 | - | 6.3 | 1.5 | 87.3 | 2.8 | 0.2 | |
| C食事のしたく 市(平成14年10月) |
0.6 | 4.3 | 0.8 | - | 92.5 | 1.2 | - | 0.5 |
| D食事の後片付け 国(平成14年7月) |
3.6 | - | 10.9 | 2.4 | 80.9 | 1.9 | 0.2 | - |
| D食事の後片付け 市(平成14年10月) |
2.3 | 7.0 | 2.8 | - | 85.5 | 1.8 | - | 0.6 |
表3資料:「男女共同参画に関する世論調査(平成14年7月)(国)
問4少子化の原因について尋ねた。(複数回答)
全体で多いのは、「子育てにお金がかかるから」「結婚しない人や晩婚の人が増えたから」「子育てと仕事の両立が難しいから」の3項目で、それぞれおよそ6割が選んでいる。このうち「両立が難しい」は、女性65.1%、男性54.4%で、差が10.7%あった。「子育ては母親の負担が大きく、父親の協力が足りないから」については、女性が35.4%に対し、男性は約半分の17.9%にとどまり、男女の差が最も大きく表れている。
子の有無によって比較してみると、全体に大きな差は見られないが、「子どもは少なく産んで十分手をかけて育てたいという人が増えたから」を選んだ割合が、子どもがいる女性で32.7%、いない女性で23.6%、子どもがいる男性で29.7%に対し、いない男性で19.3%と、やや差が見られる。
問5安心して子を産み育てるために何が必要かを尋ねた。(複数回答)
全体で割合が最も高かったのは、「出産・子育て後に再就職しやすい制度づくり」で53.8%、次いで「出産・育児に対する経済的な支援の拡充」が53.6%と、ほとんど差がなかった。
女性で多かったのは、「出産・子育て後に再就職しやすい制度づくり」(59.7%)、「出産・育児に対する経済的な支援の拡充」(53.6%)、「子育て中の柔軟な勤務形態の普及」(48.2%)、「保育サービスの充実」(47.8%)の順で、男性は「出産・育児に対する経済的な支援の拡充」(60.6%)が最も多く、以下、「出産・子育て後に再就職しやすい制度づくり」(48.8%)、「保育サービスの充実」(44.4%)となっている。回答者の割合が女性より男性の方が高かったのは、「出産・育児に対する経済的な支援の拡充」のみである。
子の有無によって比較してみると、「父親が子育てに十分かかわることができる職場環境の整備」「子育て中の柔軟な勤務形態の普及」において、男女とも、子どもがいない人の回答率が子どもがいる人の回答率より10%以上高くなっている。また、「子育て中の専業主婦のリフレッシュ支援」については、子どもがいる人の回答率が子どもがいない人の回答率より、女性で9.0%、男性で7.2%高くなっている。
問6子育てについての考え方を尋ねた。
「男の子らしさ、女の子らしさにとらわれず、個性を尊重するのがよい」が全体の6割近くを占めたが、「男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく育てるのがよい」と答えた男性は32.2%あり、女性の2倍近くになっている。また、無回答が9.0%と、やや高かった。
年齢階級別に見ると、30代、40代、50代で男女の差が大きく、「男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく育てるのがよい」と答える男性の割合がいずれも女性より20%前後高くなっている。
問7未婚者に自分の結婚についての考え方を尋ねた。
「結婚の予定がある」も含め結婚の意志がある人は約3分の2で、「今のところ結婚するつもりはない」と答えた人が23.7%いる。内訳は女性が14.8%、男性が36.0%である。
問7-1「今のところ結婚するつもりはない」と答えた人にその理由を尋ねた。(複数回答)
回答者数が全体で61人と、少ないことに留意する必要があるが、男女で理由にばらつきがあり、女性は「今の自由や気楽さを失いたくないから」が47.6%と最も多く、次に「結婚生活にともなう配偶者の親、兄弟などとの関わりを避けたいから」が38.1%となっている。男性は、「結婚して生計を維持していく自信がないから」が44.4%で最も多く、続いて女性と同様に「今の自由や気楽さを失いたくないから」が38.9%と多くなっている。
男女で差が大きいのは、「結婚生活にともなう配偶者の親、兄弟などとの関わりを避けたいから」と「結婚して生計を維持していく自信がないから」で、前者では女性が、後者では男性が、それぞれ圧倒的に多くなっている。「結婚生活にともなう家事・育児にしばられたくないから」という回答でも男女の差は大きく、女性が男性を20%以上、上回った。
また、男女とも「結婚の必要性を感じないから」が3割前後あった。
問8老後の不安について尋ねた。(複数回答)
男女とも「自分がねたきりや病気になったときのこと」(66.7%)「自分の健康のこと」(65.5%)と体のことに関する不安が大きく、「生活費のこと」(64.4%)も同様に高い割合となっている。
男女で比較すると、「自分が寝たきりや病気になったときのこと」では、女性が男性を11.3%上回ったが、反対に、「配偶者がねたきりや病気になったときのこと」では6.0%、「配偶者に先立たれること」では4.4%、男性が女性を上回っている。
問9家族等の介護が女性の役割となりがちである現状についての考えを尋ねた。
全体では「男性も女性とともに介護すべきである」と考える人が44.0%と最も多いが、男女別ではそう考える人の割合が女性の方が8.4%上回っている。また、「女性の役割だと思う」という回答は2.2%と少ないが、「問題はあるが現状ではやむをえない」として事実上、女性の役割であることを容認する割合が、女性では4分の1、男性では3分の1近くになっている。
年齢階級別に見ると、「女性の役割だと思う」が最も高かったのは60代の女性で5.8%、次いで高いのが20代の男性で4.8%となっている。「男性も女性とともに介護すべきである」の割合が最も低いのは40代の男性で、25.0%にとどまった。
問10望ましい介護のあり方について尋ねた。
男女に大きな差はなく、約半数が「自宅で、介護保険制度などのサービスを利用しながら、家族・親族が介護する」を選び、次いで高いのは「専門的な施設や病院に入って介護を受ける」の36.8%である。
年齢階級別に見ると、女性では年齢が低いほど「自宅で、介護保険制度などのサービスを利用しながら、家族・親族が介護する」が多い傾向があり、20代では60.6%に上っている。また、女性は年齢が高くなるほど、病院や施設での介護を望ましいと答えており、60代、70代では同率で44.6%となっている。男性でも、高い年齢層の方が病院や施設での介護を望ましいとする傾向があり、50代が最も高く47.7%で、「自宅で、介護保険制度などのサービスを利用しながら、家族・親族が介護する」を上回っている。
問11地域活動への参加状況を尋ねた。(複数回答)
「PTAや子ども会、青少年グループの指導など」への参加は、女性が26.8%であるのに対し男性が12.0%と、男性の割合が非常に低くなっている。「参加したことがない」は全体の約3割あり、女性が31.4%、男性が38.5%で、男性の方がかなり高い。
年齢階級別に見ると、「PTAや子ども会、青少年グループの指導など」については、女性が30代で39.7%、40代で59.4%、50代で25.1%と高くなっているのに対し、男性は30代で5.6%、40代で22.7%、50代で18.0%といずれも女性に比べて低い数値である。「趣味・教養・学習・スポーツなどのサークル活動」への参加は、女性が40代以降いずれも3割を超え、50代では約4割となっているのに対し、男性は40代で11.4%、最も高い70代でも28.0%である。
地域活動に「参加したことがない」と答えたのは、男女とも20代が最も多く6割を超えている。50代までは男性の方が多く、女性との差も大きいが、60代、70代では、女性の方がやや多くなっている。
問11-1地域活動に参加したことのある人に役職経験を尋ねた。
地域活動への参加率は女性の方が高かったにもかかわらず、役職に就いたことのある人の割合は女性が40.7%、男性が53.4%と、男性の方が高くなっている。
問11-2地域活動に参加したことがない人に、その理由を尋ねた。(複数回答)
最も多いのは男女とも、「仕事や家事が忙しく、時間的に余裕がない」で、特に男性は56.3%と、女性を10.6%上回っている。他の理由では、「健康や体力に自信がない」で男女の割合にやや差が見られ、女性は14.5%、男性が7.0%である。「家族の協力や理解が得られない」はわずかであった。
問12「男性はもっと地域社会の活動や家庭生活における活動に参画する必要がある」という考え方について尋ねた。
「そう思う」が全体の6割近くを占め、女性の方が64.0%で高くなっている。男性自身も54.0%が「そう思う」と答えている。
年齢階級別に見てみると、20代、30代で男女の差が大きく、20代では「そう思う」と答えた女性が71.1%であるのに対し、男性は45.2%、30代では同じく女性が70.1%に対し、男性は44.9%にとどまっている。男性では年齢が高いほど「そう思う」の割合が高くなる傾向が見られる。
平成12年の国の調査と比較すると、「そう思う」という回答の割合が国は73.0%で、岐阜市は国よりかなり低い。(表4)
|
項目 |
そう思う |
そうは思わ ない |
どちらとも いえない |
わからない |
無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
|
国(平成12年2月) |
73.0 | 5.5 | 17.9 | 3.6 | - |
|
市(平成14年10月) |
58.4 | 5.8 | 25.6 | 6.5 | 3.7 |
表4資料:「男女共同参画に関する世論調査(平成12年2月)」(国)
問13男性が家事、子育てや教育、介護、地域活動に積極的に参加するために必要な条件を尋ねた。
「そう思う」が最も多かったのは、「男性が、家事などに参加することに対する抵抗感をなくすこと」で全体では7割に達している。これについて「そう思う」を選んだ男女の割合の差が最も大きく、女性が男性を12.3%上回っており、また「そう思わない」と答えた男女の差も大きく、男性が女性を11.9%上回っている。
次いで「そう思う」が多かったのは、「夫婦の間で家事などの分担をするように十分に話し合うこと」で、全体の67.3%である。これについても女性が多く、71.4%となっている。
このほかの項目では、「仕事と家庭の両立などの問題について相談できる窓口を設けること」を除き、いずれも6割前後の人が「そう思う」と答えている。
問14男性が育児・介護休業を取ることについて尋ねた。
全体で88.8%が「男性も育児・介護休業を積極的に利用すべきである」あるいは「男性も育児・介護休業が取れることは賛成」としているが、男女とも「現実には取りづらい」と考える人が7割を超えている。
年齢階級別に見てみると、20代から50代までは「積極的に利用すべき」の割合が女性の方が高いが、60代以上では男性の方が多くなっている。
子の有無で比較してみると、「積極的に利用すべき」と答えた人の割合は、子どもがいない人における割合が、子どもがいる人における割合を上回っている。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
男女共生・生涯学習推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-4792 ファクス番号:058-265-8665
